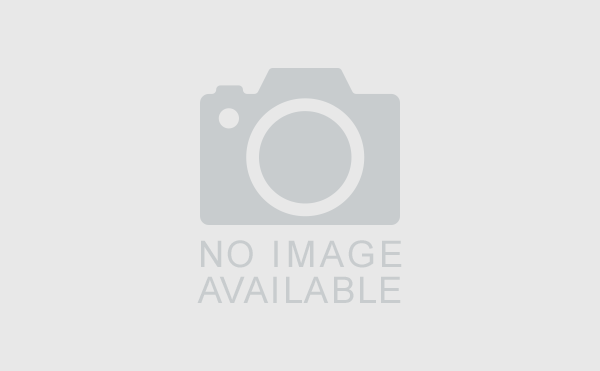Vol.22_賃金上昇時代における人事戦略
最低賃金の引き上げが続いています。
2005年の668円から、2024年には1,055円へ。そして2025年度は全国平均で1,121円程度に達し、政府は将来的に「1,500円時代」を見据えています。
この動きに対して、「生活水準の維持・向上」「賃金構造の是正(それ以上の賃金を得ている層への波及効果)」といった従業員の貢献や成長が適切に報われる方向性が示される一方で、一部の記事には「労働強化」「人員削減」といった負の側面も記載されるようになってきたように感じます。
どういうことでしょうか。
人件費=単価×人数という単純な式で考えてみるとわかるのですが、限りある人件費をどうやりくりするか、という発想に立つと、多くの経営者が最初に思い浮かべるのは「じゃあ人数を減らすしかない」という判断になるということ。これはこれで至極自然なことといえます。
その発想・判断は少数精鋭化や効率化/自動化を進めていくという方針を示唆しています。
が、それだけでは実は持続的経営としての最適解になりません。本稿では、起こりうる現実を整理したうえで、経営層・一人ひとりの従業員個人が取るべき処方箋を提示します。
起こりうる現実
賃金上昇によって何が起こりうるか。4つの視点から整理してみます。
①少数精鋭の幻想
「優秀な人だけ残せば回るはずだ」と考えるのは自然ですが、現実はそう甘くありません。アリの群れを観察した実験によると、アリの集団の中から、パフォーマンスの高いアリだけを残して、その集団がどうなるか検証しました。その結果、パフォーマンスが高かったはずのアリの中から「サボるアリ」が一定数現れたそうです。いわゆる“2・6・2の法則は普遍的なもの”ということを示唆しています。
つまり、サボり組を切り捨てても、時間が経てばまた新しいサボり組が生まれる。
「少数精鋭(人数は少ないが、優れた能力や高い専門性を持つ人材だけで構成された集団)」は、最初はうまく見えても、残念ながら持続性がないと言えるのです。
➁生産性向上の限界
もちろん、無駄やムラを削れば効率は上がります。しかし、それにも上限があります。様々な事例や経験則に基づくとおおむね15%程度の効果と言われています。さらに言えば、余白や遊び部分まですべて削ってしまえば、事故発生・品質不良・納期遅延という別のデメリットが顕在化することになりかねません。体脂肪がゼロだと逆に健康を損なうリスクが高まるように、余剰や余白が全くない組織も、かえって不健全になりがちです。
③人件費配分のジレンマ
仮に「1人を1,500円/1Hで雇う」のと「2人を750円/0.5Hずつで雇う」のとでは、同じ人件費でも意味が違います。前者は質が求められる業務や一定の責任を任せることは可能ですが、量をこなすことは不可能ですし、欠勤や退職のリスクは大きい。後者は持続性や柔軟さはあるけれど、人材の質がブレるリスクがあり、また個別の教育や調整のコストが増えることになります。
要は、お金の額面は同じでも“人件費の配分設計”次第で勝敗が変わるのです。
④正社員と非正規の溝がさらに深まる
そしてもう一つの現実。
正社員は“個”として配慮や調整を受けやすいのに対し、非正規は“塊”として扱われがちということです。現場の実務を支えているのはむしろ非正規であることが多いと言われている中で、同じ人間でありながら、「個」と「道具」としての扱いの差が存在するのは皮肉なことと言えるでしょう。
経営の処方箋
では、経営としてどう備えるべきか。
ここで必要なのは「削る発想」ではなく「設計する発想」と筆者は考えます。
具体的には・・・
- 人件費は“総額”で考えるのではなく、誰にどう配分するかの発想を持つこと
- 現在の業務の質・量、分担・負荷の状況、繁忙時期などを可視化すること
- 正社員・非正規という線引きではなく、役割と期待値を明確にすること
- シフトの下限や休憩確保といった“安全余白”をKPIとして守ること
- 定型業務はテクノロジーに置き換え、人は付加価値に専念させること
こうした発想の転換が、最低賃金上昇を単なる“コスト増”から“競争力の源泉”に変えることができるのではないでしょうか。
個人への処方箋
もちろん、一人ひとりの個人も「会社に守られている」思考に留まっていては危ういといえるでしょう。
具体的には・・・
- 自分がどこで戦うべきか、また労働市場での自分の位置を把握すること
- スキルを複線化し、1時間の単価を押し上げること
- 成果をデータや事例で示し、交渉材料とすること
- 収入や経験の源を分散し、最低賃金の揺れに左右されないこと
こうした行動が「選ばれる存在」への近道になるといえるでしょう。
まとめると
最低賃金の急激な引き上げの流れの裏で、会社側が何を考えていくか。第一反応として人数削減や労働強化というテーマに直面していくことになると思われますが、それだけで対応が終わる会社は、いずれ競争力を失い、最後は大事な人材も去っていく可能性が高いと考えます。
経営に求められるのは、効率化や削減ではなく設計力です。効率や削減は現場の仕事です。
そして個人に求められるのは、受け身ではなく主体性です。
「少数精鋭の幻想」に頼るのではなく、「配分と育成の設計」に踏み込めるかどうか。
それこそが、2026年以降の明暗を分ける経営の鍵になるように思います。