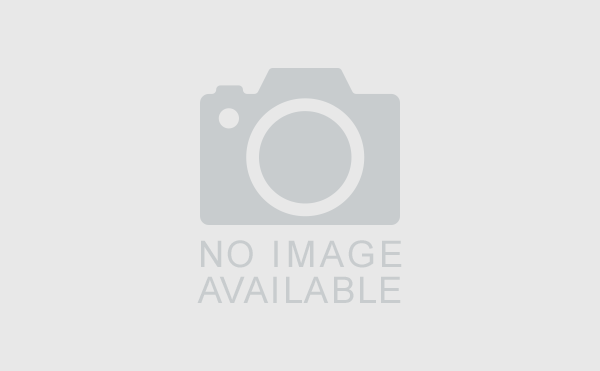Vol.24_“公平”って、そもそもなんですか?
あるジレンマに直面したら?
唐突ですが、あなたは人事部長です。
次年度の役職者人事を検討するシーズンです。継続させるのか、退任させるのか、だれを充てるのか――
ある事業部門の課長ポストを検討していたときのお話です。
60歳間近のベテラン社員がいます。長年の経験と人脈を持ち、周囲からの高い信頼をあり、組織にとって欠かせない存在です。
一方で、同じ部署には5人の中堅社員がいます。大変有能でさらに成長経験を積んで、これからの組織のリーダーとして期待される人たちです。
もし空きポストがひとつしかないとしたら――
あなたは、ベテランの雇用を延長しますか?
それとも中堅5人の成長機会を優先しますか?
2つの事例から考えてみましょう
ある大手メーカーA社では、2020年代前半から定年を65歳に延長しました。狙いはシンプル。経験豊富な人材をできるだけ長く組織の中核に残し、知見を継承してもらうことでした。
延長後、ベテラン社員に管理職ポストを任せると、大口顧客との取引が安定するとともに、中堅・若手だけでは維持できなかった案件もスムーズに続けられました。また、熟練の現場社員が安全管理や技能伝承の軸となり、事故率も低下しました。
一方、サービス業B社では、同じく65歳まで定年を延長しつつ、リーダー育成を狙いとして、40歳代の中堅社員を管理職ポストに充てることにしました。ベテラン社員には培ってきた強みを活かして専門分野に特化し、他メンバーの知見・技能向上や悩み相談にも注力してもらいました。新たなリーダー自身や他メンバーたちの中にあった漠然とした不安もいつしか解消でき、一人ひとりが自信をもって業務に取り組めるようになり、コミュニケーションや連携もこれまでにないくらい活発で、一人ひとりが組織全体のレベルアップに少しずつ貢献できるようになりました。
2つの事例の違いはなにか?
同じ「定年延長」の事例ですが、A社とB社はまったく異なる未来を描くことになりました。
- A社の選択:候補者全員を公平に見て、これまで貢献してきた人に引き続き活躍の場を与える
- B社の選択:世代の強みや経験等を公平に踏まえ、役割分担を考え、次世代にバトンを渡す
どちらも成果を出すことはできました。けれども「公平」の定義が違うようです。
ここに、答えのない問いが隠れています。
思い込みを解きほぐしてみよう
この問いを考える上で、多くの人がつい陥ってしまう“思い込み”があります。
例えば、「定年を延長すれば人手不足は解決する」という発想です。
確かに短期的には戦力を確保できますが、役割の設計を怠れば、かえって組織の硬直化を招きます。
また、「若手に席を譲ることが公平だ」という考え方もあります。
しかし、その場合、高齢社員が培ってきた経験やネットワークは十分に活かされないまま失われてしまいます。それは本当に公平でしょうか。
さらに「60歳を過ぎれば誰もが能力を落とす」といった決めつけも根強いですが、実際には個人差が大きく、むしろ年齢を重ねても高い成果を上げ続ける人や新たな領域に挑戦し、さらに成長を続ける人も少なくありません。
こうした“あるある”の思考パターンは、つい分かりやすい答えに飛びついてしまう私たちの習性を映しています。けれども、その裏にある多様な要素を見逃すと、問題を一面的にしか捉えられない事態に直面します。すなわちA社とB社の事例が示すように、制度の設計次第で結果は変わり、そこに“唯一の正解”は存在せず、どちらのやり方でも成果を上げることはできるのです。
線を引く基準はどこにある?
では、どんな視点で考えると、この問いを少し深く掘れるのでしょうか。
一つ目は「公平の基準は何か」
年齢という単純な基準で一律に判断するのか、それとも能力・貢献度・将来性といった多面的な指標を組み合わせるのか。この基準の置き方次第で、制度の姿は大きく変わります。
二つ目は「持続可能性の視点」
今の世代を守ることが、次の世代の負担にならないか。たとえば人件費が固定化されすぎれば、将来の投資余力を奪いかねません。
三つ目は「多様性との関係」
DEI(ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン)が叫ばれる中で、年齢の多様性をどう活かすかは無視できない論点です。年齢を理由に役割を一律に制限することは、多様性推進の逆行にもなり得ます。
四つ目は「社会と企業のバランス」
社会的には高齢者雇用の確保が要請されますが、企業には競争力を維持する責任があります。この二つをどう折り合わせるかは、人事制度設計を超えた社会的かつ戦略的課題といえるでしょう。
A社とB社の違いも、この視点で「定年延長」による対応を眺めると理解しやすくなります。
A社は「公平=機会平等」と定義しましたが、B社は「公平=役割分担」と考えたのではないでしょうか。
どちらが正しいかは一概に言えません。しかし、線を引く基準の違いが、組織の未来を大きく左右することだけは確かです。
公平とはそもそも何なのか?
日本語でよく使われる「公平」という言葉の意味を少し検討してみましょう。
実はとてもあいまいに使われていると思うことはないでしょうか。
- 平等(equality) … 誰にでも同じ条件を与えること。
- 公正(equity ) … 状況や必要に応じて調整し、結果的に釣り合いをとること。
これらをA社・B社の事例に沿って整理してみると、A社の公平とは「平等」を指し、B社の公平は「公正」を指しているように思います。
同じ“公平”という言葉を使っていても、その中身は違うことが分かります。
だからこそ「公平とは何を意味するのか?」という問いが議論の過程で生まれることになるのです。
あなたならどちらに共感しますか?
公平とは、全員を同じようにとらえて、より適材に機会を与えることなのでしょうか。
それとも、状況に応じて異なる役割を設けることなのでしょうか。
もしあなたが経営者・人事責任者なら、どちらの「公平」に共感しますか?
あるいは、あなた自身の「公平」の定義はまた別にあるでしょうか。
おわりに ― 問いを持ち続けましょう
どちらが正しいかではなく、どう考えるかが大事です。
「世代間の公平 × 定年延長」というテーマは、簡単に逆転しない普遍的な結論が出るような答えはありません。
けれども、組織がこの答えのない問いを考え続けることこそが、自分たちを次のステージへと押し上げる力になると確信しています。
みなさんの職場では、どんな“公平”が存在していますか?