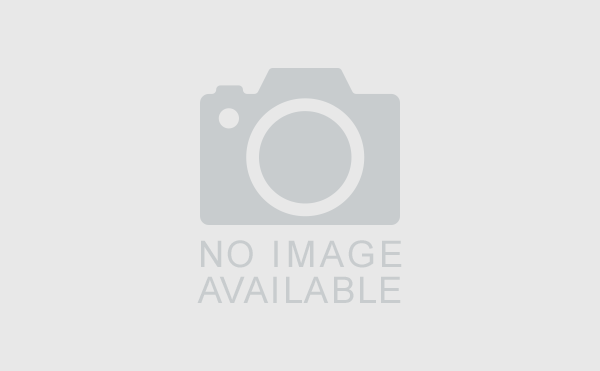Vol.25_「人材不足」の誤解
“人が足りない”とはなにか?
最近、どの業界でも「人が採れない」「求人を出しても応募がない」という声をよく聞きます。
一見、労働力人口の減少が直接の原因のように思えますが、実は数字を見てみると少し違う姿が見えてきます。
総務省統計局の労働力調査によると、2024年時点の労働力人口は約6,900万人。10年前からほとんど減っていません。非正規雇用者を含めた就業者数も、コロナ期を除けばむしろ増加傾向にあります。
つまり「人がいない」のではなく、「企業が欲しいと思う人が足りていない」のではないでしょうか。
求人倍率をみてみましょう。
厚生労働省「一般職業紹介状況」によれば、すでに1.3倍前後で高止まりしていますが、実際には「採用に困っている業界」と「人が余っている領域」がはっきりと分かれています。
建設・介護・物流などの現場系や、IT・デジタル・営業などの即戦力職種は常に人手不足と言われています。
一方で、ホワイトカラーの一般事務や販売職では応募が集中します。
つまり、「人材不足」とは、“総量の不足”ではなく、能力・賃金・勤務地・働き方の不整合や、企業と候補者の関係性の希薄化 、といった”構造的なミスマッチ”が問題の本質と考えられます。
また賃金を十分に上げ、柔軟なシフト・場所・裁量を提示してもなお充足しない領域がある一方、条件調整で応募が回復する職種もあります。一律の総量論だけでは説明できないのが実態です。
本当の問題は「質」と「関係性」
企業が「人が採れない」と感じる背景には、二つの要因があります。
1つはスキルや経験の質のミスマッチ、もう1つは関係性の断絶/希薄化です。
1つ目の「質のミスマッチ」とは何でしょうか。
例えば、DXや新事業開発など、必要なスキルが急速に変化しているのに、教育や評価制度が追いついていない状態を指します。その結果、「できる人」は一部の市場価値の高い人材に集中し、その他の層は“可もなく不可もなく”と見なされてしまうのです。これをシンプルに表現すると、「採れるけど活かせない」「活かしたいけど採れない」――この矛盾が、企業の現場に人材不足感をもたらしていると言えます。
2つ目の「関係性の断絶/希薄化」とは何でしょうか。
1つ目よりももう少し深い話となります。かつては地域や職場でのつながりを通じて自然に人材が流動していました。
ところが今は、仕事探しがプラットフォーム上の“条件マッチング”に置き換わり、「どんな会社か」よりも「どんな条件か」が重視されるようになっていませんか?
企業側も“数字で測れる即戦力”ばかりを追う結果、「人と人の関係をどう育てるか」という視点が抜け落ちているように感じます。
“採用できない”のではなく、“惹きつけられない”
実際、「採用できない」企業の多くは、“惹きつける力”の設計ができていません。
求人広告を出して待つだけでは、もう人は来ません。
転職サイトの情報を見ても、どこも似たようなコピーが並んでいます。
「風通しの良い職場」「挑戦できる環境」「ワークライフバランス」――
それらは誰の会社でも言えてしまう言葉です。
一方で、同じ規模・同じ業界でも採用に成功している企業があります。
彼らは“知名度”ではなく“リアリティ”で勝っています。
たとえば、自社サイトの採用ページで社員の仕事ぶりを動画で見せたり、
業務委託や副業から関わってもらう「関係づくり型採用」を行ったり、「まず関わってみる」「一緒に考えてみる」――
そうした“関係づくりから始まる採用”が、無名企業の勝ち筋になりつつあるようです。
数ではなく「関係の質」で見る時代へ
採用とは、本来「会社が選ぶ」行為ではなく、「会社が選ばれる」行為です。
つまり、一見すると企業が選ぶ立場に見えますが、実際には候補者が企業を選んでいます。
これは労働市場の需給状況とは関係なく、構造が変わっていることを示唆しています。
この構造変化に気づかないまま、求人だけを量産しても結果は変わりません。
人材を確保できている企業の共通点は、「量の確保」ではなく「関係の設計」にあります。
例えば、社員紹介(リファーラル)やアルムナイ(卒業社員)との関係維持、業務委託やプロジェクト型副業による“関係の入り口”の多様化など。
これらはすべて、“関わりの継続性”を中心に設計されています。
言い換えれば、人材確保とは、“採る”ということに注力するよりも、“つながる”ことなのです。
人を「雇う」から「関わる」。採用の本質は変化しており、企業と個人の関係は、契約ではなく共感で動くように変わりつつあることに気付けるかどうか、がポイントといえるでしょう。
採用活動をどうデザインすればよいのか
いま問われているのは、「どう採るか」ではなく、「どう関わるか」です。
人が集まらないという現象の裏には、“働く側の論理”を見落とした企業構造があります。
つまり、採用の問題はマーケティングの問題であり、関係性デザインの問題でもある。
求人を出して待つ時代から、関係を設計して惹きつける時代になりました。
次回は、最近のトレンドといえるスポットワーク(例:タイミー)をどう活用すべきか、検討してみたいと思います。