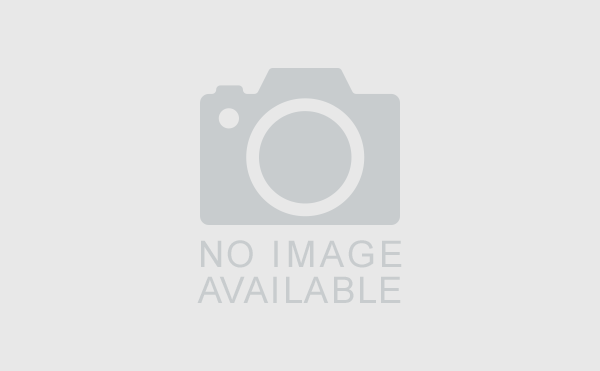Vol.23_美術館で幸福感を味わってみよう
突然ですが、この画像の風景、どこを撮ったものか分かりますか?

これは、東京・南青山にある根津美術館のエントランスにつながる通路です。
2023年の夏、竹と石が整然と並ぶこの通路に足を踏み入れた瞬間、思わず息をのみ、「これは、すごい!」と心の声が出たことを今も覚えています。
光と影のコントラスト、竹の緑の濃淡、石畳の質感。写真でも十分衝撃を受けると思いますが、実際に現地で見た時の高揚感や躍動感は全くことなります。空気の匂い、静寂の中に響く足音。その場でしか感じ取れない空気があるのだと強く実感したものです。
美術館は「作品を見る場所」だと思われがちです。けれど実際には、入口に立ったその瞬間から、すでに芸術体験は始まっているのです。ぜひ一度足を運ぶことをお勧めします。
美術館で得られる様々な経験
私は美術館・ミュージアムに行くことが好きです。地元だけでなく、出張先・旅行先でも時間があれば見に行きます。
知っている作品を見に行くというワクワクさ、知らなかった作品に出会ったときの新鮮さ。作品の解説を読み、作品に秘められた意味や物語を知る。正直に言えば、作品ごとの記憶は家に帰る頃には薄れてしまうものです。でも、、、時間が経過するとまた美術館に行きたくなります。
なぜなのか。それは美術館全体の雰囲気や流れる時間が頭の片隅に刻まれているからではないかと思うのです。
この夏に青森県立美術館を訪れたときは、建物だけでなく、芝生や周辺施設を含む敷地全体が「ひとつの作品」のように感じられました。巷では有名な《あおもり犬》を見るためには館内を一度出て、遠回りをしなければなりません。その“わざわざ感”に探検のような物語性やワクワクを自然に感じたものです。

東京・上野にある国立西洋美術館では、とにかく膨大な作品に圧倒されました。時間がなくて速足で巡るしかなかったのですが、教科書や雑誌で見たことがある作品も多く、「勉強になる空間」だった印象があります。さらに、作品の前で学芸員と美大生グループが鑑賞しながら議論している光景も目にしました。美術館は一人で没入する場所であると同時に、人と人との対話を誘発する場でもあるのだと後になって感じたものです。

一方、愛知県美術館でパウル・クレー展を観たときは少し違いました。名古屋・栄の中心街にあり、大規模な建物構造に圧倒されました。また美術館内はとにかく「音」への配慮が徹底されていて、わずかな鈴の音にさえ係員から注意を受けるほど。子どもと一緒に訪れていた私には緊張感が強すぎて逆に疲れる部分もありましたが、静寂を徹底して守る、という一面もその美術館の個性なんだろうと思います。そしてその疲れさえも一種の余韻が残っています。

国内外にまだ行くことができていない美術館にたくさんあるのに、随分と偉そうに語って良いものなのか微妙ですが、一人の少ない経験から振り返ってみると、訪れた美術館ごとに全く違う体験があったように思います。
探検のワクワク、高揚する非日常、知的な刺激、あるいは厳粛すぎる静寂。他の類型もあるかもしれませんね。
あなたなら、どのタイプの美術館がしっくりくるでしょうか?
ところで、すべての美術館で共通していたのは、「幸福感が残る」ということです。読書の「読後感」に似ています。
作品を一つひとつは覚えていないのですが、幸福感=リフレッシュした感覚を持ち帰ることができ、しばらくその感覚に浸っていた記憶がありました。
他のリフレッシュ方法と比べると・・・
美術館でのこの体験、カフェや散歩や旅行とどう違うのでしょうか。
カフェで過ごすひととき。自宅にはない空間や雰囲気に接すると甘いチョコレートのように一瞬で心を和らげてくれます。でも、店を出た瞬間に効果が切れてしまうことが多いように感じます。
旅行は盛りだくさんで大皿料理のようにぎゅっと詰まった満足感がありますが、日常に戻れば一気に現実に引き戻されます。記録や思い出を振り返らないと、あっという間に忘れてしまうものです。
その点、美術館は少し違います。言葉に落とせないけれど、「心に酸素が充填されたような感覚」が長く残るのです。静かな空間に身を浸した余韻が、日常に戻っても薄れにくいのです。
美に触れる意味を考えてみる
作品を覚えていなくても、「幸福感だけは残る」。実はこの“余韻”を充填することが、不確実であいまいさであふれる現代社会の中で自分の軸=主観を育てるものだと思うのです。これが他のリフレッシュとの決定的な違いのように思います。
別の視点で考えてみましょう。論理的には「どれでもいい」と言える状況でも、最後に選ぶには感性や主観が決め手になることが多いのです。
たとえば名刺デザインをどうするかといった場合。複数案を見比べても「どれも悪くない」状態では決められません。最終的に決めるのは“これが自分にしっくりくる”という感覚です。
また、目標を「To do(やること)」ではなく「To be(あり方)」で考えるときも同じです。「売上を上げる」ではなく「顧客に信頼される存在でありたい」と考える。その価値観やあり方の基準には、論理ではなく感性=Senseが関わっています。
美術館で得られる幸福感は、この「感性」を育てるものだと思います。積み上げるものではなく、自分の中にあるものを磨くという考え方がしっくりくるかもしれません。
例えば・・・・
- 選択肢の中から「自分らしい」ものを選ぶ軸を磨く
- 目的そのものを再定義する力を磨く
- 他者との違いを受け入れ、対話を可能にする感性を磨く
つまり、美術館は「曖昧さを乗り越える力を充電する場所」ではないか、と思うのです。
美術館へ行ってみませんか?
美術館は、作品を暗記する、とか、正解を探す場ではありません。むしろ、作品を忘れてしまってもいい。残るのは、心が整う幸福感です。
根津のエントランスで感じた高揚、青森の探検感、国立西洋の知的刺激、愛知の厳粛な静寂。どれも感じ方や印象は違いますが、共通しているのは「行ってよかった」という余韻でした。
あと少しすれば、“内面を豊かにする活動”が似合う季節がやってきます。
心を整えに、ふらっと美術館に足を運んでみたらいかがでしょう。
その非日常的な空間や雰囲気はきっと、あなたの心に酸素を満たし、日常を少しだけ軽やかにしてくれるはずです。